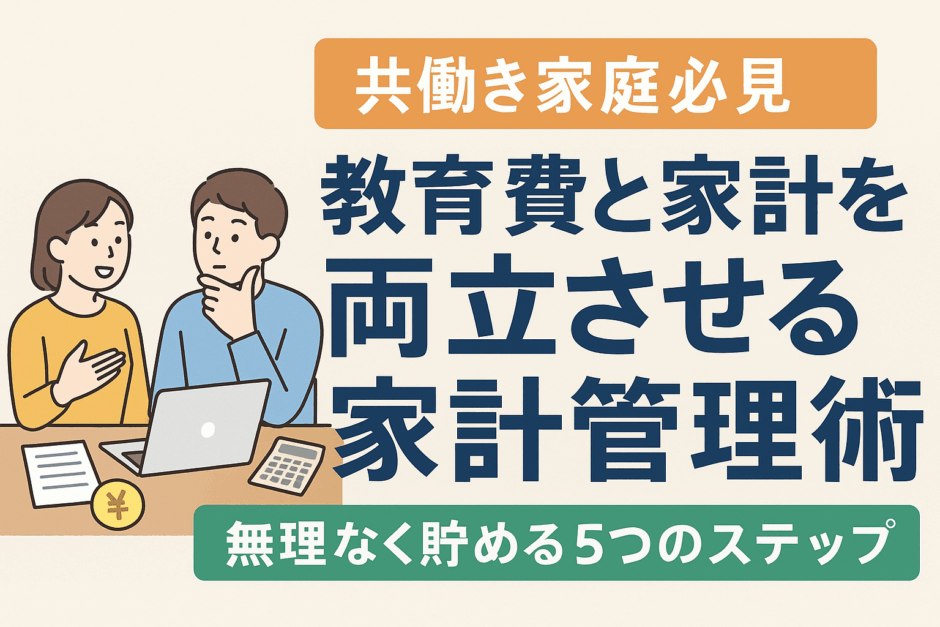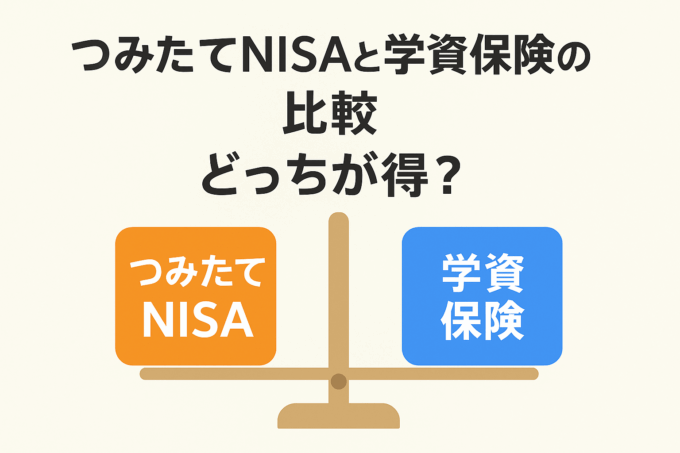「共働きだけど、なかなか教育費が貯まらない…」
仕事と子育てを両立しながら家計をやりくりするのは、想像以上に大変ですよね。
教育費は年々上昇傾向にあり、計画的に積み立てないと大学進学時に一気に負担が増えるケースも少なくありません。
この記事では、共働き家庭が無理なく教育費を貯めるための家計管理術を、5つの実践ステップでわかりやすく紹介します。
教育費は“月いくら”を目安に貯めるべき?
文部科学省のデータによると、幼稚園〜大学までの教育費は1,000〜2,500万円。
共働き家庭であっても、毎月の収入から「教育費専用の積立」を確保することが重要です。
教育費の貯蓄目安は、月収の10〜15%。
たとえば手取り月35万円の家庭なら、毎月3〜5万円を教育費用に積み立てておくと安心です。
ステップ1:教育費専用の口座をつくる
まずは「教育費専用口座」をつくりましょう。
生活費とは完全に分けることで、使ってはいけないお金を明確に区別できます。
- 給与振込口座とは別に銀行口座を用意
- 児童手当やボーナス時に自動振替を設定
- 毎月の固定積立(1〜3万円)を自動化
教育費口座を見える化することで、貯蓄の進捗が実感でき、モチベーション維持にもつながります。
ステップ2:学資保険で“確実に貯める仕組み”を作る
共働き家庭では「忙しくて家計を見直す時間がない」という声が多く聞かれます。
そんな方におすすめなのが学資保険。
自動で積み立てられるため、強制的に教育費を貯める仕組みを作ることができます。
また、契約者に万一があっても払込免除特約で保険料が免除されるため、確実に満期金を受け取れる安心感があります。
具体的なおすすめプランは、【2025年版】学資保険おすすめ5選を参考にしてください。
ステップ3:児童手当を“使わずに貯める”
児童手当は0歳から中学卒業まで支給され、総額はおよそ200万円前後になります。
これを生活費に使わず、教育費口座や学資保険に回すだけで、大きな違いが生まれます。
児童手当の支給月(2月・6月・10月)に、そのまま自動振替する設定をしておくと、無駄なく貯められます。
ステップ4:つみたてNISAで“上乗せ資金”を育てる
余力があれば、つみたてNISAで教育費の一部を運用するのも効果的です。
非課税で長期積立できるため、10年以上のスパンで運用すればインフレにも強く、複利で資金を増やせます。
ただし、リスクを取りすぎないように注意。教育費の「最低限必要な部分」は学資保険などで確実に確保しておくことがポイントです。
ステップ5:家計簿アプリで“見える化”する
共働き家庭では、夫婦間で「お金の流れを共有する」ことも重要です。
最近は、家計簿アプリで銀行口座・クレカ・電子マネーをまとめて管理できるようになっています。
おすすめアプリ:
- マネーフォワード ME:教育費の残高や積立進捗をグラフで確認可能
- Zaim:支出項目を細かく設定して「教育費比率」を分析
毎月の「教育費積立額」と「支出実績」をチェックするだけでも、使いすぎ防止につながります。
まとめ:共働きだからこそ“自動で貯まる仕組み”を
教育費は「気づいたら足りない」では手遅れです。
共働き家庭ほど、仕組みで貯まる家計設計が重要。
教育費専用口座・学資保険・児童手当・NISAなどを組み合わせて、手間をかけずに貯まる仕組みをつくりましょう。
今日の小さな行動が、10年後の大きな安心につながります。