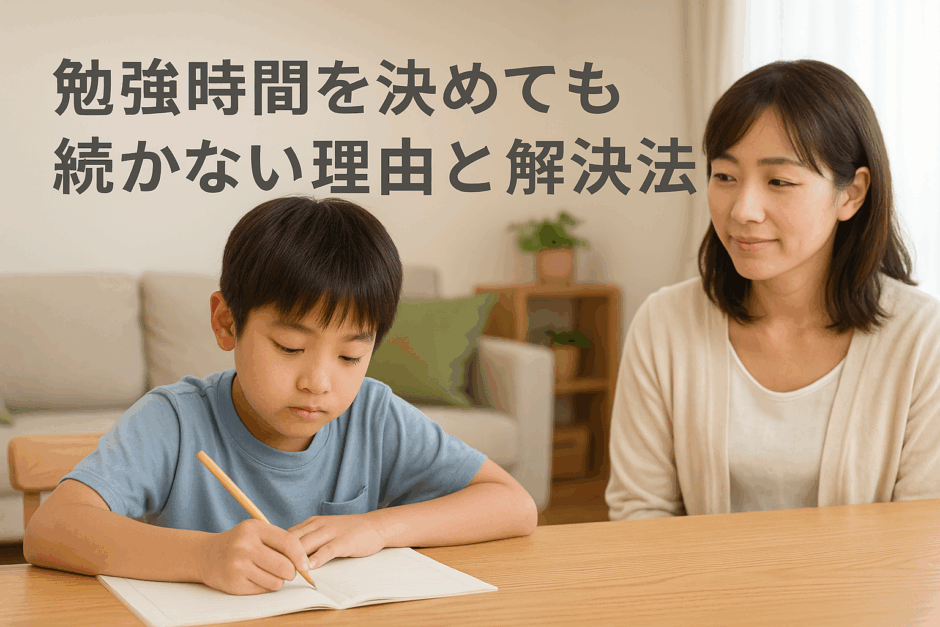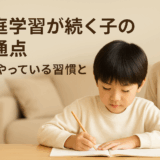なぜ「勉強時間を決めても続かない」のか?
「毎日◯時から勉強しようね」と決めても、数日で終わってしまう…。
そんな経験はありませんか?
実は、子どもが勉強を続けられないのは「やる気がない」からではなく、習慣化の仕組みがうまくできていないことが原因です。
脳は“面倒なこと”を避けようとする性質があるため、環境や親の関わり方次第で「続く」「続かない」が大きく変わります。
勉強が続かない子に共通する3つの特徴
① 目的があいまいなまま始めている
「なぜ勉強するのか」が本人の中で整理されていないと、すぐに飽きてしまいます。
「勉強しなさい」よりも、「これができるようになったら嬉しいね」と、達成イメージを一緒に描くことが大切です。
② 勉強時間が“長すぎる”
集中力は年齢×1分が目安。
小学生なら10〜15分単位で区切るのが理想です。
最初から1時間やらせようとすると、「もう無理」と脳が拒否反応を起こします。
③ 親が「監視」になってしまっている
「早くやりなさい!」「まだ終わってないの?」と急かされると、
勉強=プレッシャーになり、机に向かうこと自体を避けてしまいます。
親は“見張り役”ではなく、“応援者”の立場で寄り添うのが効果的です。
続けられるようになる!5つの習慣づくりのコツ
① 「時間」より「タイミング」で決める
「◯時から勉強」ではなく、「夕食の前」「お風呂のあと」といった“行動のセット化”が有効です。
人は「行動の連続」で習慣をつくる生き物。
決まった流れの中に勉強を組み込むことで、自然と続けやすくなります。
② 最初は“超短時間”から始める
勉強を続けるコツは「成功体験を積ませること」。
最初の1週間は10分でOK。できたら一緒に喜びましょう。
「できた!」という感覚が、次の行動のエネルギーになります。
③ 親も一緒に“静かな時間”を共有する
子どもにだけ「勉強しなさい」と言っても効果は薄いです。
親も同じ時間に本を読んだり、日記を書いたり。
「親も頑張ってる」と感じると、子どもは安心して取り組めます。
④ 「できたこと」を見える化する
勉強カレンダーやチェックシートを使って、続いた日を視覚化しましょう。
シールを貼るだけでも、達成感とモチベーションが生まれます。
特に低学年の子には“視覚的なご褒美”が効果的です。
⑤ 結果より“過程”を褒める
「テストで100点」よりも「昨日より集中できたね」「時間を守れたね」と、
努力や継続そのものを褒めることが大切です。
これが“続ける力”を育てる一番の近道です。
続ける力を育てるのは「親の安心感」
勉強を続けるための一番のエネルギーは、実は「安心感」です。
「頑張ってるね」「今日もやってるね」という小さな承認を重ねると、
子どもは「自分はできる」と信じられるようになります。
習慣は、結果よりも“心の土台”から育つのです。
まとめ:続けることを目的にしないのが“続く”コツ
大切なのは、「毎日やること」ではなく、「今日も少しできた」を積み重ねること。
勉強が“義務”から“日常の一部”に変わったとき、子どもの目は確実に変わります。
焦らず、比べず、一歩ずつ。「続く仕組み」を一緒につくっていきましょう。