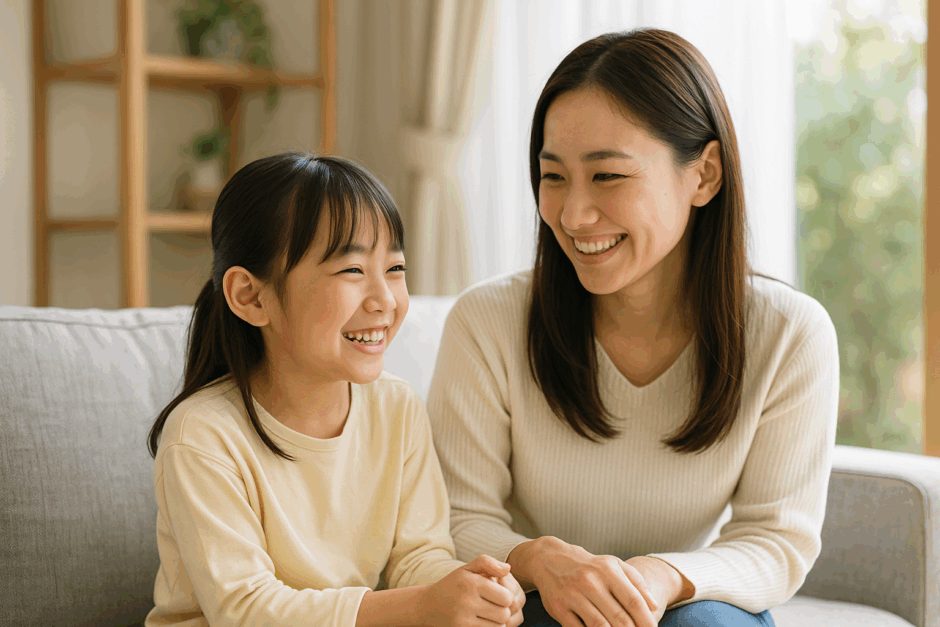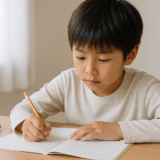「どうせ自分なんて…」そんな言葉が出ていませんか?
「うちの子、すぐに“どうせ無理”って言うんです」
そんな悩みを持つ親御さんは少なくありません。
実はそれ、子どもの自己肯定感が下がっているサインかもしれません。
自己肯定感とは、「ありのままの自分を受け入れられる力」。
これが低いと、挑戦を避けたり、失敗を恐れたりする傾向が強くなります。
しかし、親の関わり方次第で、子どもの心は今日から少しずつ変えられます。
自己肯定感が低い子どもの特徴
自己肯定感が低い子は、次のような行動や言葉をよく見せます。
- ・失敗を極端に怖がる
- ・うまくいかないとすぐに「もういい」と諦める
- ・他人と自分を比べて落ち込む
- ・褒められても「そんなことない」と否定する
- ・叱られると必要以上に傷つく
一見「性格の問題」のように見えても、実は家庭内での言葉の積み重ねが大きく影響しています。
自己肯定感を下げてしまう親の言葉・行動
自己肯定感が低い子どもは、親の何気ない言葉から「自分はダメだ」と感じてしまうことがあります。
① 比較してしまう
「〇〇ちゃんはできたのに」「お兄ちゃんを見習って」
こうした比較の言葉は、子どもにとって“自分は劣っている”という刷り込みになります。
② 否定形の指摘が多い
「まだやってないの?」「何回言えばわかるの!」など、注意や叱責が続くと、
子どもは「どうせ怒られる」と思い、挑戦する前に諦めてしまいます。
③ 結果だけを評価する
「100点ならすごい」「勝ったから褒める」といった評価は、
“結果を出せないと価値がない”という誤った認識を生みます。
努力の過程を認めることが、心を育てるカギです。
家庭でできる!自己肯定感を育てる5つの方法
① 結果ではなく「努力の過程」を認める
「結果はまだだけど、そこまで頑張れたね」
この一言が、子どもの心に“自分は認められている”という安心を与えます。
特に小学生期は、失敗よりも“過程の価値”を伝えることが大切です。
② 否定ではなく「提案」で伝える
「ダメ!」ではなく「こうしてみようか」。
同じ注意でも、言葉のトーンを変えるだけで、受け止め方がまるで違います。
この“提案型の声かけ”は、教育心理学でも効果が実証されています。
③ 小さな成功体験を積ませる
勉強・生活・遊び、どんな場面でも「できた!」という瞬間を意識的に作りましょう。
成功体験の積み重ねが、“自分にもできる”という自己効力感を育てます。
たとえば通信教育やワーク教材を使って、毎日数分で達成感を得られる仕組みを取り入れるのも効果的です。
④ 「あなたがいてくれて嬉しい」を言葉にする
自己肯定感の根底にあるのは、“存在の承認”。
「勉強できるから好き」ではなく、「あなたがいるだけで嬉しい」と伝えることが、
子どもの「無条件の安心感」を育てます。
⑤ 親自身が「自分を認める姿」を見せる
自己肯定感は、家庭内でモデリング(模倣)によって学ばれます。
親が「今日はちょっと頑張れた!」と自分を認める姿を見せると、
子どもも“自分を認めていいんだ”と学びます。
体験談:自己肯定感が低かった娘が変わった瞬間
筆者の娘は小学2年生のころ、「私なんてできない」が口ぐせでした。
叱っても変わらず、むしろ自信を失っていく姿に悩みました。
そこで、点数を褒めるのをやめ、「前より集中できたね」「ここまで頑張れたね」と声を変えたのです。
数週間後、娘の口から初めて「できた!」という言葉が。
親の言葉が、子どもの“心の辞書”を作るのだと実感しました。
心理学でわかる「褒める=自己肯定感の土台」
ポジティブ心理学によると、人は1つの否定を打ち消すのに3つの承認が必要とされています。
つまり、叱るよりも褒める機会を3倍にするだけで、
子どもの自己肯定感は確実に回復していきます。
家庭での声かけを「否定ゼロ週間」と決めてみるのもおすすめです。
まとめ:自己肯定感は“親の言葉”で育つ
自己肯定感は、特別な才能ではなく、日々の小さな会話の積み重ねで育ちます。
「あなたの存在を大切に思っている」というメッセージを、言葉と行動で伝え続けること。
その安心感が、子どもの心の根っこを強くしていきます。
焦らず、比べず、少しずつ。親子で“自分を認める練習”を始めていきましょう。